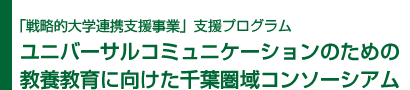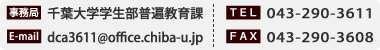応用教育カリキュラム開発
- ・敬愛大学国際学部で「ユニバーサルコミュニケーション(手話)」の開講
- ・新規授業「バリアフリーコニュニケーション入門」の開始
- ・授業科目「NPOインターンシップ」の共有化(企画)
- ・新規渡日留学生向け映像教材の作成・試行
- ・手話への取り組み(城西国際大学)
敬愛大学国際学部で「ユニバーサルコミュニケーション(手話)」の開講
このたび、城西国際大学と敬愛大学の間で、バリアフリー教育に関する情報が共有・活用された結果、敬愛大学国際学部でも平成23年度より「ユニバーサルコミュニケーション(手話)」(1年次開講/選択科目/2単位)が開講されることになりました。
新規授業「バリアフリーコニュニケーション入門」の開始
授業科目「NPOインターンシップ」の共有化(企画)
現在4大学での共通授業の開設に向けて検討を行っています。
- →企画書

新規渡日留学生向け映像教材の作成・試行
■事業概要:
現在千葉大学には1000名近い留学生が在籍しており(2009年5月1日現在957名)、これらの留学生に対しては、毎学期留学生のニーズや日本語のレベルに合わせた様々な日本語授業が開講されている。しかし、海外から直接千葉大学に留学する者に対しては、通常の授業とは別に、基本的な生活環境を円滑に構築し、本学における学習環境に速やかに適応できるよう、来日直後の早い段階から支援をする必要がある。
大学院段階のプログラムの多様化に伴って、今後日本語未習の留学生が増加するものと見込まれており、特に留学生の6割近くを占める中国からの留学生を対象とした支援ツールの必要性は喫緊のものとなっている。
本教材は、日本語未習の新規渡日留学生に対し、映像を通して、基本的な生活情報およびコミュニケーションの手段としての必要最低限の日本語表現を教えるものであり、日本語編、生活編の二つに分かれる。
日本語編は以下の9つの場面からなる合計90分の映像である。
(1)空港から寮まで編、(2)寮到着編、(3)買い物編、(4)自己紹介編、(5)学食編、(6)先生との食事編、(7)郵便局の手続き編、(8)病気編、(9)非常事態編
一方、生活編は以下の6つの場面からなる合計60分の映像である。
(1)入国手続き、電車移動、(2)入寮手続き、寮周辺情報、(3)飲食店情報、携帯電話等手続き、(4)区役所手続き、寮から区役所や大学までの行き方、(5)国際教育センター、食堂利用方法、(6)入国管理局、バス・自転車の乗り方
本教材は新規渡日留学生の本学における円滑な学習環境構築の支援を主な目的とするが、これによってさらに、大学生活における講義・自習等の様々な場面における日本人学生・他の国や地域からの留学生とのコミュニケーションの可能性も飛躍的に高まるため、本教材運用の改善によって本学学生全体のユニバーサルコミュニケーション能力を向上させることが見込まれる。
■取組の計画:
(1)コンテンツ作成計画具体化のための映像素材等の試作
大学の関連各施設間および郵便局や区役所などの施設へのアクセス支援ツールとして、画像(写真)と地図を組み合わせた以下のコンテンツを試作した。
a.ワードファイル(日本語版・英語版・中国語版・韓国語版)
国際交流会館から国際教育センターまで
国際交流会館から稲毛区役所まで(往復)
西千葉キャンパスから緑町郵便局まで
成田空港から国際交流会館まで(中国語版のみ)
b.ウェブ掲載用ファイル(日本語版のみ)
http://www.international.chiba-u.ac.jp/navi/top.html
国際交流会館から国際教育センターまで
国際交流会館から稲毛区役所まで(往復)
西千葉キャンパスから緑町郵便局まで
西千葉キャンパスから松戸キャンパスまで(往復)
平成21年度前期に渡日した国費研究留学生にaを配布し、試用に供した。21年度後期も試用する予定である。
(2)コンテンツ作成作業
- ・日本語編:日本語未習の留学生が、渡日後すぐに日本語が必要になるであろう場面を中心に、先に挙げた9場面を設定し、それぞれの場面の台本を、ひとりの中国人留学生を主人公に会話形式で作成。それらを映像化し、9枚のDVDに収録した。現在は、付属教材となる語彙リスト、文型リスト等を作成中である。
- ・生活編:留学生が渡日後すぐに直面するであろう場面を中心に、先に挙げた6場面を設定し、それぞれの場面に中国語のナレーションを付して、6枚のDVDに収録した。
※なお、このコンテンツ作成については、「グローバル30経費」により実施。
(3)コンテンツ運用の改善と応用のための試験的運用
上記(2)で作成した留学生支援コンテンツを、携帯用再生端末(i-Pod)を利用して実際に留学生に使用してもらい、使用した学生へのアンケート・聞き取り調査により、運用方法・運用場面・類似コンテンツとその運用の可能性等について改善・応用計画を策定する。
■使用した機材等:
- ・ビデオカメラ等動画撮影機材一式(1)
- ・デジタルカメラ等(1)
- ・動画・静止画・webサイト等編集ソフト(1)
- ・試験的運用のためのiPod(2)および(3)
■これまでの取り組み状況および今後の計画:
平成20年度は、画像と地図を組み合わせた、大学の関連各施設間および郵便局や区役所などの施設へのアクセス支援ツールを作成し、3つの言語に翻訳した。平成21年度には、平成20年度に行った試作をもとに、紙媒体およびwebページで、そのアクセス支援ツールを新規渡日留学生に提供し、その反応をコンテンツ作成計画の具体化のための参考資料とした。[上記(1)]
平成21年度には、平成20年度の試作および試作コンテンツの試験的運用をもとに、生活編・日本語編からなるDVD教材(中国語版)を作成中である。日本語編については、さらにDVDを活用するための付属教材の開発も予定している。完成と同時にこれも留学生を対象とし、本学学生全体のためのユニバーサルコミュニケーション教育(主に外国語・外国文化理解)教材への応用を期して試験的に運用する予定である。[上記(2)および(3)]
平成22年度には、平成21年度に作成したコンテンツおよびその試験的運用によって得られたデータを参考に、留学生支援コンテンツ運用の改善技法を開発するとともに、これを別に開発中の日本人学生向け外国語・外国文化教材運用の改善に応用する予定である。[上記(3)]
手話への取り組み(城西国際大学)
福祉総合学部の学生を中心として、手話への取り組みを推し進めており、千葉聴覚障害者センターより講師の派遣を受け、手話の技術的指導を受けるとともに聴覚障がいに対する理解とコミュニケーション能力の向上を図っている。また、課外活動での手話勉強会も行われており、これらを通じて手話に習熟した学生達は手話への理解と普及に目を向け始め、1つの方法として「手話コーラス」に取り組んでいる。
現在、手話コーラスは大学祭やシンポジュウム、オープンキャンパス等の機会を通じて発表を行い、日頃手話に触れる機会の少ない方々が手話への理解を得る契機となるよう活動を継続している。
また、教養教育プログラムに向けたコンテンツ作成を試行しており、ビデオ撮影等のテストを行っている。
手話コーラス発表